コラム
- コラムトップ
- ステルスマーケティング(ステマ)とは?概要や問題点、リスク回避のための対策をご紹介
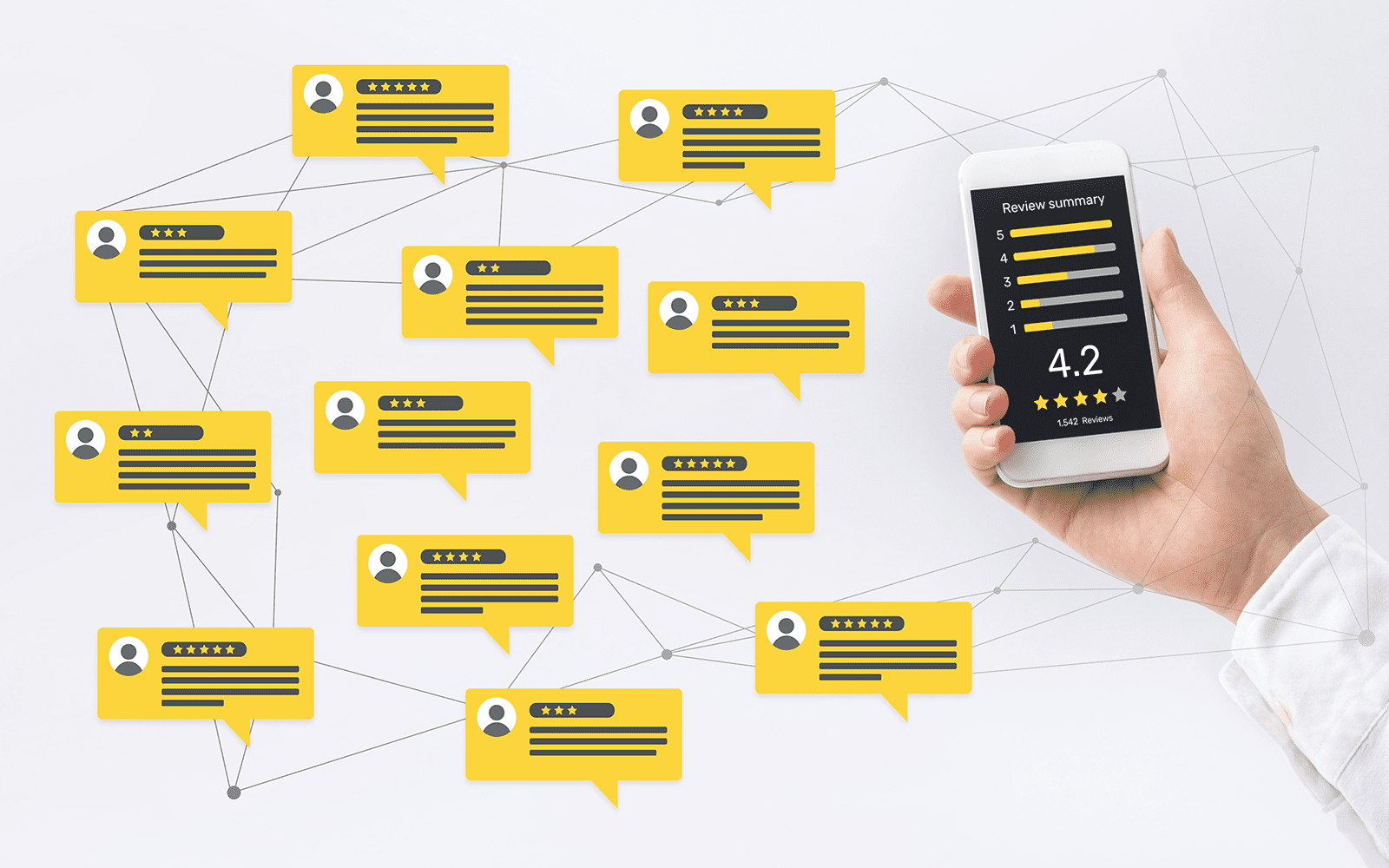
ステルスマーケティング(ステマ)とは?
概要や問題点、リスク回避のための対策をご紹介
ニュースやSNSでもよく耳にする「ステマ」。商品やサービスを買う消費者様を惑わす、不正なマーケティング手法として知られています。この記事では、ステマの概要や問題点・リスクなどに触れた後、主にインターネット広告を出稿している企業(広告主)様に向けて、行うべきステマ対策をご紹介しています。
商品/サービスを提供する事業者様はもちろん、掲載側(媒体様)の方にも参考にしていただけると思いますので、ぜひご覧ください。
ステルスマーケティング(ステマ)とは?
ステルスマーケティングとは、消費者様に向けて、宣伝や広告であることを隠して行う販促行為のことです。略してステマとも言われています。stealth(ステルス)は日本語で「隠密」「こっそり行う」などと訳せますので、言葉通りそのままの意味です。以前から悪い行為として認識されている手法で、令和5年10月1日からは景品表示法(景表法)に違反する行為となりました。景品表示法は、「景品」と「表示」それぞれに対して規制が設けられているものですが、ステマは「表示」に関する規制の一つになります。
では、「隠して行う宣伝」とはどのようなものでしょうか?
ステマは主に2つの類型に分類して説明されるので、具体例とともに紹介します。
①なりすまし型
事業者が自ら表示しているにもかかわらず、第三者が表示しているかのように誤認させるものを、消費者庁はなりすまし型と分類しています。これはつまり、商品/サービスを提供する企業の関係者が、企業と関係ない第三者を装って商品の宣伝をする行為などを指しています。
- 例:
- ショッピングサイトで販売している商品について、販売元の社員が一般消費者を装って良い口コミを投稿し、本当の利用者の声と誤認させ販売を誘引する
②利益提供秘匿型
事業者が第三者に金銭の支払いやその他の経済的利益を提供して表示させているにもかかわらず、その事実を表示しないもの。これを消費者庁は利益提供(秘匿)型としています。具体的には以下のようなケースです。
- 例1:
- 影響力のあるインフルエンサーにお金を渡し、PRであることを隠してSNSに商品の投稿をしてもらい、インフルエンサーが普段愛用しているものかのように誤認させる
- 例2:
- 第三者にクーポンを提供し、良い口コミを投稿してもらう
第三者にお金を支払いPRの依頼をすることは本来広告になります。利益を得て宣伝している事実・広告であることを隠して発信してしまうと、それはステマに該当します。ただし、金銭含め経済的利益の提供の有無は最重要事項ではなく、無報酬で行った宣伝でも、宣伝行為ということを隠せばステマと見なされる可能性があります。
なお、ここで言う「表示」とは、消費者様の目に触れる商品/サービスに関する情報全般です。商品ラベルに書かれた原材料や価格等はもちろん、販促のために行う広告などの表記も含まれます。具体的な例は、下記参照元のガイドブック(5ページ目に記載されているので、参考にしてみてください。
ステマになるものとならないもの
ではどういったケースがステマになってしまうのでしょうか?線引きが難しいと思うかもしれませんが、基本的には「事業者の表示(と認められるもの)」がステマ規制の対象です。反対に「事業者の表示とはならないもの」は規制対象外になります。ただ、事業者様自らが行った表示でなくても、事業者の表示と認められればステマの規制対象になる、というのがポイントです。
ステマ(ステルスマーケティング)の規制対象となる表示
事業者の表示と認められるものが規制対象となります。第三者が行った発信でも、事業者が表示に関わったと見なされれば規制の対象になります。
-
- 事業者自身で行う表示
- 商品/サービスを提供する事業者が第三者を装っている、もしくは第三者による発信と誤解させるもの
- 事業者が第三者に依頼・指示して表示させたもの(事業者が表示の決定に関与したもの)
- 事業者が明らかに依頼・指示していなくても、第三者に表示させた場合と判断されるもの
など
インフルエンサー様などの第三者が商品/サービスに関する表示をして、それがステマ規制に抵触する可能性がある場合、事業者様とのやり取りや関係性、対価の内容等を調査され、総合的に見て事業者の表示となるか否かが判断されます。
ステマ(ステルスマーケティング)の規制対象とならない表示
客観的な状況に基づき、事業者の表示と見なされないものはステマの規制対象外です。
-
- 第三者の自由な意思による表示(表示内容に関して事業者からの指示ややり取りが一切なく、自主的な表示・投稿と認められるもの)
- その他、広告であることが明らかなもの(テレビCM、ラジオCM、新聞・雑誌の広告欄や、公式サイト/公式アカウントでの発信など)
など
消費者庁が制作している以下参照元のガイドブックでも詳しく説明がありますので、ご覧ください。
ただ誤解がないように言うと、事業者様ではない第三者が表示(広告等)すること自体が問題なのではなく、広告であることを隠したり、実際に商品/サービスを利用した方の中立的な口コミであると誤認させてしまうことが問題になります。消費者様の誤認が起こるとどうなるかや、誤認させないような対策は、次の章以降で説明します。
ステルスマーケティング(ステマ)の問題点
宣伝行為ということを隠してPRすることの問題は、一言で言えば、消費者の方が商品/サービスを自主的・合理的に選べなくなることにつながる点です。
消費者様は普段、物の購入やサービスの契約など、お金を使うものを自由に選択することができますが、ステマが横行してしまうと商品/サービスについて適切な評価・選択ができなくなってしまいます。消費者の方は、広告であることを分かった上で商品/サービスの表示に触れれば、企業側の伝えたいメッセージのみが凝縮された販促物であると、ある程度身構えて情報を見ることができます。逆に広告であることが隠されてしまったり、わざと良い評価にした口コミばかりが世の中に広がれば、信頼できる第三者の口コミや、客観的で中立的な評価はどれなのかがわからず、企業が販促のために出している情報との区別ができないことで、商品/サービスに対しての合理的な判断・選択が阻害されてしまいます。
ステマ規制が含まれる景品表示法自体が、消費者様が良い商品/サービスを合理的・自主的に選べる環境を守るための法律なので、すべてはそこに帰結するわけです。
また、インフルエンサー様やアフィリエイター様などの情報発信者が、悪い行いとわからず無自覚に企業様からの依頼を受けたり、広告である旨の明示をしていないケースもあり、その認識の甘さも問題視されています。
ステルスマーケティング(ステマ)のリスク
ステルスマーケティングに抵触の可能性がある事案が発生した場合、消費者庁の調査が入り、総合的・客観的に鑑みてステマと判断されれば景品表示法違反となります。違反した際には、必要に応じた「措置命令」が下されます。
- 措置命令
- 違反行為の差止め、再発防止策の策定、会社や商品名が(違反の旨とともに)公になってしまうなど
景表法違反の制裁としてもう一つ「課徴金納付命令」というものがありますが、ステマ告示のみに違反する場合には、この課徴金納付命令の対象にはなりません。
ただ、措置命令が下されるほか、ニュースやSNSで取り上げられ世間的に企業の信頼度が下がったり、消費者の方の対応に追われたり、広告活動に制限がかかるなど、多くのデメリットがあります。
ステマ規制の違反の際、ペナルティの対象となるのは商品/サービスを供給する事業者であり、事業者(企業)から宣伝の依頼を受けたインフルエンサー様などの第三者は対象外です。ただし、規制対象となる表示にはインフルエンサー様の投稿やアフィリエイトサイトなども含まれます。つまり、第三者のSNS・Webサイト等で違反になっても責任を追うのは広告主様ということになります。
ステマ規制の正しい知識と理解がないまま販促を行っていると、意図せず加害者になってしまうことも考えられます。そのため、消費者の方へ商品/サービスを提供する企業様が広告を出稿する際には、ステマの概要の理解とルール化やチェック体制を整えた上で広告等のPR展開をすることが望ましいです。
インターネット広告とステマ
景表法・ステマは、販促を行うあらゆる表示媒体(ネット、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌など)が対象になる法律ですが、主にインターネット上の広告や口コミで問題になることが多く、Webマーケティングを展開する際には注意が必要です。
ネット広告の中でも特に気をつけたいのが、インフルエンサー様に頼んでPRしてもらう類のものや、アフィリエイト広告。これらは広告主様の作った広告クリエイティブ(バナー等)をそのまま表示させる形式ではなく、第三者が商品/サービスについての感想や紹介文を作成して掲載することが多い広告手法なので、消費者の方は利用者の客観的な口コミなのか、企業様の広告として感想を述べているものなのか、とりわけ区別がつきづらい傾向があります。
それにもかかわらず、広告である旨の記載がないまま広告が掲載されている状況が今なお散見されます。令和5年10月にステマが消費者庁に指定告示されるまで、消費者の方に向けて広告であることを明示する重要性があまり語られてきておらず、まだまだ広告主様や媒体様にその理解とルールの浸透ができていないことが理由の一つです。媒体様・インフルエンサー様などの広告を掲載してくれる第三者に、掲載内容をすべて任せきりにしたまま未管理状態の広告主様も一部いますので、利益(広告費)提供していることを隠す意図はなくても、結果的に隠されてしまっているケースが多いと推察できます。
このような状況があるため、消費者庁はもちろん、広告主様や広告代理店、ASP(アフィリエイト広告を出稿できるサービス)などがステマ規制について啓蒙し、消費者の方が安心して合理的・主体的に購入や契約できるように対策していくことが急務です。
アフィリエイト広告は特に、広告を掲載する側はブログやSNSなどのアカウントがあれば副業でも始められる参入ハードルの低さが特徴です。景表法やステマについて深く知らない方も多くいますので、法律上責任を負うことになる広告主様が、主体となってステマ対策を推し進めることが重要です。
アフィリエイト広告の概要が知りたい方は以下の記事もご覧ください。

【広告出稿を検討中の方向け】アフィリエイト広告とは?概要をわかりやすく解説
アフィリエイト広告とはWeb広告の一つで、成果報酬型の広告です。Web広告は掲載することで費用が発生するものや、ユーザーへ広告が表示されたら費用が発生するものなど、種類と費用形態が様々あります。
広告主様が講ずべきステマ対策
知らずに加害者とならないために、広告主様ができるステマ対策をいくつか紹介します。
①広告は広告の旨の明示を徹底する
インフルエンサー様・アフィリエイター様など第三者である媒体様にPRを依頼する際には特に、消費者の方に向けて広告である旨を明示してもらう対応と掲載面のチェック・管理が必須です。書き方については媒体様側のサイト・SNSのトンマナに合わせて任意になるため細かい指定ができない場合もありますが、以下のような例示に沿っている必要があります。
- 【対象媒体】
-
- SNSの投稿
- Webサイト(比較サイト、ランキングサイト等)
- ブログ
など
広告の掲載ができるすべての媒体が対象です。
※なお、Instagram、X、YouTube等のSNS媒体や、アフィリエイト広告の場合はASPによってもそれぞれポリシーやルール、レギュレーションがありますので、それらも遵守するよう媒体様に伝えてください。
- 【広告を掲載する際に表記すべき文言例】
-
-
広告とわかる文字
「広告」「PR」「プロモーション」「アフィリエイト広告」等 -
広告とわかるフレーズ
「この記事には広告が含まれています」
「当ページにはアフィリエイト広告を利用しています。」
「A社から商品提供を受けて投稿しています」等
-
広告とわかる文字
- 【表記する位置の例】
-
- サイトのヘッダー
- 広告を掲載している各記事の上部
など
ただし、上記の例示はごく一部で、他にも望ましいとされる文字の大きさや色などの指定もありますので、詳しくは消費者庁のHPにてご確認ください。以下PDFに細かい表示の例が記載されています。
媒体様と金銭のやり取りがなくても、同様に対応するのが望ましいです。例えば、商品やサービスを無償提供したケース。商品を提供したことで、SNSへ商品に関する投稿をしてくれる可能性がある際には、「広告」「PR」等の文言をつけて発信してもらうことを徹底しましょう。厳密に言えば、広告主様が表示(投稿)の内容の決定に関与していなければステマとはならないわけですが、この場合においては、商品を受け取った媒体様の自由な感想であるか、広告に該当するのかは非常に曖昧な線引です。消費者庁の[ステルスマーケティング告示ガイドブック]では、事業者が明示的に依頼・指示していなくても、やり取りや対価の有無、関係性により第三者に表示させたと見なされるとNGとあるので、投稿の際は広告の明示を必須にルール化するのが一番安全です。
②社員向けにSNS投稿に関するルールを設ける
意図せず「なりすまし型」のステマを行わないための対策です。一人一つ以上、SNSのアカウントを持つのがあたりまえになった現在。企業に属する社員が、個人アカウントで身分を明かさず、自社商品/サービスに関する投稿をした場合、「広告」「PR」などの表記がなければ景表法違反になる可能性があります。子会社や、販促・開発に関わる取引先の社員も対象に含まれるため、商品/サービスに携わる社外関係者を含め、SNS投稿時のルールづくりの上、厳守するよう体制を整えることが賢明です。なお、販促目的ではない投稿や、一般消費者様にも知り得る範囲の情報発信であればステマとならない可能性はありますが、消費者様や行政に販促目的だと判断されてしまえば違反になります。一番安全なのは個人アカウントでの商品/サービスに関する投稿を一切NGにすることですが、どうしてもPRに個人のSNSを活用したい場合には、アカウント情報や投稿に会社関係者である旨の明記や広告表記などを徹底しましょう。
また、ステマ対策にもつながる景表法全般についての対策を、消費者庁が以下で発信しています。合わせてご覧ください。
こちらの記事でも、内容を要約しています。
まとめ
ステマについての概要と広告主様ができる対応をご紹介しました。
売上を伸ばすためのマーケティング施策は色々ありますが、知らずにステマに該当する行為を行っていたということのないように対策し、消費者の方が安心して商品/サービスを選択できるような環境を整えていきましょう。
